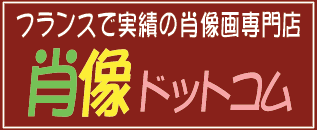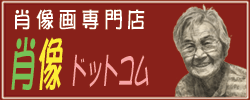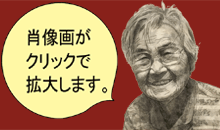- トップ
- エッセイ
- 世界貿易センターと建築家
世界貿易センターと建築家
作家山田風太郎の言に、「我が命は地球より重い。他人の命は犬より軽い」というのがあった。
友人・知人、一度でも面識のある人の訃報に会ったならば、誰しも胸が塞がる思いがするであろうが、マスコミで日常茶飯事のニュースにおいて、見たことも聞いたこともない人が死んだという報に、本当に心を痛める人は多くない。
昨年の9月11日の同時多発テロのことを書こうとしているのだが、ビンラディン・アルカイダの悪逆非道さに心底憤り、同国人の不幸に心から涙したアメリカ人たちが、祖国アメリカの軍隊によるアフガニスタン爆撃に際し、誤爆により多数の民間人を死なせた事実に、胸を痛めた人々が多数いたようには思えない。
戦争反対をアピールした自国の女子高生を退学させたというニュースもあった。誰も責めることはできないと思う。人間とはそうしたものだ。
あのニューヨークのツインビル・世界貿易センターが崩壊したとき、真っ先に私の頭に浮かんだこと。それは何よりも、あの建築がもう見られなくなった、という喪失感だった。

建築を学ぶ学生だった私は、1980年二十歳の夏渡米し、あのツインビルの真ん中にあったベンチに寝転がって、頂上を真下から眺めたものだった。
エンパイア・ステートビルのようには先端が尖っていない方形ビルのため、真下から見ると、頂上がはっきり天とは断ち切られているのがわかる。垂直性を強調した簡潔なデザインとあいまって、天にそびえる摩天楼の風格には乏しいというのが、当時の建築雑誌による評判だった。私は自分の目でそれを確かめたかったのだ。

世界貿易センターは日系二世の建築家ミノル・ヤマサキの設計である。ツインビルの形体はヨーロッパの双塔の大聖堂から得られたもので、デザインは簡潔だけれども、それはまさしく彼自身の様式に違いなく、とてもよくニューヨークの空気にマッチしていた。
私はこの建築が一辺で好きになった。高く偉大な存在に対する憧れ。それを見事に体現していた。日系移民二世だった建築家ミノル・ヤマサキ。今から27年前、世界経済の中心に世界最大のツインビルを建てた彼は当時得意の絶頂だったろう。
彼の作品の特徴はシンプルなデザインと縦長の窓の採用である。近代以前の建築ような装飾は一切剥ぎ取られているから、禁欲的にも見える。外観の単調さは、建築の使われる用途に応えるために最大の空間を確保することを目的としたことから派生したもので、建物の機能と効率を最大限に高めた結果なのだ。
この辺の事情を建築家磯崎新がうまく説明していた。
「近代建築で最も重視されたのは効率性だ。建物の中が最も効率良くつかえて、デベロッパーにとってぎりぎりの投資で最高の効果が得られるプランとデザインを良いとする論理だ。これを徹底するとオフィス空間はいかなる事態が起こっても取り換え可能な融通むげな内部が求められる。究極的には建築の形はどうでもよくなり、単なる箱に近づく。
実際、ニューヨークでは板を並べた構造のロックフェラーセンターができたころから箱型の構造体が増えた。貿易センタービルは人間の文化的活動を飛び越えて効率性を極めたという点で、近代建築の暗部というべき建物だった。
ビルの上部が教会の塔のイメージを引きずっているエンパイア・ステートビルやクライスタービルは、近代建築が純化する一歩手前の建物だ。」
“近代建築の暗部”と謳っているのは、磯崎が世界貿易センターのデザインに対して批判的であるためだろう。私はデザインに関して不満はない。まさに20世紀という時代を如実に反映する建築物であり、モニュメントであると思う。しかし別の意味で、このビルは近代建築の暗部だと今は断言できる。
さて、その前に建築家ミノル・ヤマサキの人物について触れてみよう。
以下は、月刊アトリエ’88年11月号『ミノル・ヤマサキの業績』(文・阿部徹雄)より抜粋。
ミノル・ヤマサキは富山県からの移民二世として1912年12月1日シアトルに生まれる。ワシントン大建築科卒。在学中の夏休みにはアラスカのサケ缶詰工場で学資を稼ぎ、修士過程はニューヨーク大の夜間部という苦学生だった。その後人柄の良さを買われて、エンパイアステートビルを建設した事務所に就職、国連ビルを手掛けた事務所でも働く機会を得た。1955年に完成したセントルイス空港の設計で一躍注目されるようになり、1974年の世界貿易センタービル(地上110階、高さ412メートルのツインビル)で名声を高めた。この45年間に世界で300ほどの建造物に携わり、現代において最も多くの仕事をした建築家といえる。日本でも都ホテル東京など3つがある。1986年2月6日デトロイトにて癌のため死去。享年73。
彼の共感するエマーソンの“美”と題されたエッセイ。
「美は必要性の中に存在する。美が形成されるのは、完璧な経済性の結果としてである。ミツバチの巣は、最少の材料で最大の強度を得るように造られる。また鳥の骨や羽は、最も軽くて最大の頑丈さを持っている。自然の構造の中には無理な部分はひとつもない。植物の持つ色彩や形態には、その必然性に対する強い理由がある。建築という芸術は、熟練した技術で材料を最大限に節約するものであり、その美は、壁からできる限りの重量を剥ぎ取って、柱の持つ詩情にその強さを包み込むことで達成される。」
彼の言葉。「私は世界旅行で、人類の建築史上で至宝といわれるものを数多く見て来たが、建築家が誰であれ、その建築がどこにあろうと、そうした偉大な作品には共通した一つの特徴が見られる。それは、日の出から日没までを通じて、太陽の光の変化が最大のインパクトを創り出す。
そして最後に彼自身の衝撃的な言葉をもう一つ紹介する。「ビルの寿命はせいぜい20年です。私はそう割り切って設計しています。といいますのは、これから10年後どんな生活環境になるのかいま明確に私はつかめていないんです。それなのに20年後を考えてみても見当がつかない。20年前に建てたビルが、現在の職場環境で極めて不便なものになっていますが、それよりももっともっとかけ離れた状態で今、建てつつあるビルの20年後の姿は悲しい残骸になると私は思っています。それほどこれからの時代のテンポは早く変貌してゆく。したがって我々は現在最も機能的なビルを造ると同時に、いかに造っておいたら不適当になった時、短期間に壊せるかを考えています。その壊すまでの年月を20年とみているんですよ。
私は14年前の古い美術雑誌の、彼の文章を目にして、息を呑んだ。
2001年9月11日、同時多発テロの日。アルカイダのメンバーが乗っ取った飛行機がセンタービルに激突したとき、被害はその上下のフロアだけで、階下はそのまま残るだろうというのが大方の予想だったし、私も飛行機が突き刺さったまま残り、死傷者は出たとしても大した数にはのぼるまいと思った。だが数十分後2つのビルは全崩壊した。
崩壊原因について新聞は報じた。「貿易ビル“ドミノ崩壊”か」と。東工大教授が言うには、新しい高層ビルは柱や床の鉄骨を溶接で組みたてる工法をとっている。横揺れには強いが上からの衝撃は想定されていない。鉄骨が溶けて床が下階に落ちて行くことで、次々に床が抜けて行ったのではないか。古いエンパイアステートビルのような鉄筋とコンクリートで固められた建築なら上部が崩壊するだけですんだかもしれない、と。
米ABCテレビは、貿易センタービルは鉄骨がビルの周囲にしかないチューブ状構造をしており、上層階が崩壊するとドミノ倒しのように下層に過重がかかると報じた。2つのビルを支える地下構造物が一体になっていることを原因に挙げたメディアもあったがいずれも言い尽くせていない。
竣工からすでに27年たっている。ミノル・ヤマサキの言う20年の寿命は越えている。だから、ビルが不要になった時点で爆破することによって、あのように上から下まで一瞬に崩壊するように、建築家は設計していたのだ。つまりあのようなビルの最期を予め見越していたのだ。おそらく鉄骨の溶接工法も最小限にして、リベットのようなピン接合だけで繋ぎ止めていたのではなかったろうか。
私は昨年来、あの美しいツインビルが失われたことの感傷にひたっていた。20世紀の建築家として最高の名声を得て死んだミノル・ヤマサキ。自らの代表作がよもやあんな形で、ハイジャックした飛行機を用いたテロでたった27年で消えるなんて予想だにしなかっただろう。芸術家の不運を思わずにはいられなかった。
しかし、事実はそうではなかった。建築家は二十数年後に世界貿易センタービルが失われていることを知っていた。アルカイダの自爆テロは除くとしても、一瞬で見事に眼前から消え去ることを計算していたのだ。建造物をわざとそのような構造にしていたのだ。まるで手品師のように。

いや、これも、2つの大戦やさまざまな民族対立による虐殺・破壊行為、また大量生産による環境破壊・人体汚染など、20世紀に生まれた人間すべてによって生み出された、合理性による数々の災厄のひとつなのだ。
1931年に建造されたエンパイアステートビルはオフィスビルとしては陳腐化しているにもかかわらず、当時の先端技術だった鉄筋コンクリート工法を最高度に駆使した結果、より長い耐久性を保持している。そして冠たるモニュメンタリティーを抱いて今も聳え立つ。このビルの設計者はビルの寿命が20年だなどとは考えもしなかったに違いない。
「古いものほどしっかりしている」というのは、真実である。古い時代ほど緻密な学問がないから経験則からものを創り出す。新しいものを初めて創るなら、これ以上はできないというような最高に頑丈なものを造らざるを得ない。しかし、現代は細分化した学問が高度に発達した結果、同じく学問から生まれた設計基準をぎりぎりに満たすものを造るという芸当ができるようになった。まったく愚かなことだ。完璧な学問などあるはずがないのに。
そして一方、「もろく消えやすいものは美しい」というのも真実ではある。夕映えの世界貿易センタービルを海上から撮った写真を表紙に用いた今年のカレンダーがあった。差替えるのも間に合わなかったためだろうが、その光景は本当に美しかった。
願わくは、これからの建築家がミノル・ヤマサキのような手法を採らないことを祈る。すべての芸術家が永遠に残る作品を創ることを祈る。すぐ失われるようなヤワな素材を用いたり、写真や映像に残ればいいのだなどと考えず、資源を浪費せず、技術的に、耐久性に優れた作品を創ることを…。
(02/03/09)