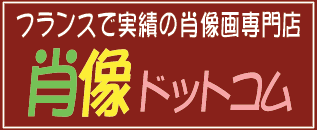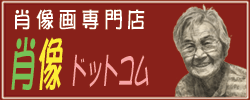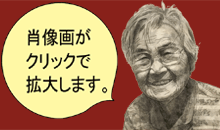- トップ
- エッセイ
- セザンヌ論
- 目は、同じ色彩を追い求める
- 目は、同じ形を追い求める
- 目は、同じ明るさのものを追い求める
- 目は、同じ大きさのものを追い求める
- 目は、矢印が指し示す方向を追いかける
- 目は、お互いに似たもの同士を1つのものとして、まとめる傾向がある
- 明るい色は手前に、暗い色は奥に引っ込んで見える(明暗対比)
- オレンジ色など暖かい色は手前に、青や緑など冷たい色は奥に引っ込んで見える(寒暖対比)
- 補色やそれに近い色を隣接させると、お互いに補色をかけあって、一層鮮やかに見せる(補色効果)
セザンヌ論
|
 |
これは形態の調和をもたらす『プレグナンツ(懐胎)の法則』といいます。
ポール・セザンヌ(1839~1906)という人は、このような考えを意図的に用いて、見る側の視線の誘導を最も効果的に行った画家
だと思います。このプレグナンツの法則を、セザンヌの絵に則して言い直してみましょう。
それから、プレグナンツの法則から離れますが、
さて、これらをざっと踏まえた上で、実際にセザンヌの絵を見てみましょう。『トランプをする人々』です。(これは今 回の展覧会で私を最も楽しませてくれた絵です。30分近く見ていたと思います。) まず最初に何があなたの目に入るでしょうか? 目 は最も刺激の強いものに吸い寄せられます。仮にトランプの白だとしましょう。では、トランプの白を見つめたときに、あなたの目は次に 何を見つけるでしょうか? おそらくほとんどの人は、同じ白いものに目が行くと思います。右の男のシャツの衿が白いですね。左の男の 口にくわえたパイプも、衿も白いです。中央のワインの壜にも白くハイライトが置かれています。右の男のトランプにも弱い白が点じられ ています。
左の男の顔のオレンジ色に、最初に目が行った方もいらっしゃると思います。左の男の顔に目を向けてみましょう。その
瞬間に、目は同じオレンジ色 を求めて、右の男の顔に飛びます。男たちのこぶしにも、テーブル掛けの中にも、ワインの栓にもオレンジ色が
見られます。
を求めて、右の男の顔に飛びます。男たちのこぶしにも、テーブル掛けの中にも、ワインの栓にもオレンジ色が
見られます。
では、オレンジ色だけを線でつないでみましょう。なんとなくWを形作ってはいませんか? 白色はどうですか、同じく Wが見えてきませんか? さらに男たちの肘を見てください。やはりWを作っているのが分かると思います。セザンヌは同じ形を巧妙に反 復させているのです。 また、二人の肘は、二つのポケット、背広の裾、テーブルの二つの脚と響き合っています。
次に気づくことは何でしょう。何だかテーブルが左に傾いていませんか? これは、セザンヌが画面に動きを待たせるた めに、意識的にデフォルメさせているのです。このテーブルの脚と同じく傾いているものは、左の男の背もたれですね。平行線です。 ワインの壜とそのすぐ右の黒い棒のようなものも同様に傾いています。窓の桟もそうです。右の男の膝も同じ角度です。
右の男の帽子のつばを起点にしてみましょう。視線はピンと跳ね上がって、左の男の帽子のつばに落ち、目は男のなだら
かな肩をすべり落ちます。椅子の背もたれに沿って画面下端まで降りた視線は、背広の裾を伝って右に上がり、テーブルに沿って右の男の
ポケットまでたどり着きます。ここで右の男の肘も背広の皺も、ポケットも上方を志向しているのに気づきます。また、黒いズボンも、
右上のブルーグレーの空間へ誘導します。そこから視線は、窓に沿って左に抜けて行きます。左に抜けても、同じような平行線はいくつも
用意されているので、すぐに目は戻ってきます。
(起点はどこからでも構いませんし、どんな順番でも構わないのです。あなたの感じたままに画面を旅してください。)
こうして、鑑賞者の目はセザンヌの操るがままにくるくると動き回り、色彩の豊かさもあいまって、飽きるということが ありません。いつまでもずっと楽しませてくれるのです。言い方を換えれば、まさに見る人の目を釘付けにしてしまうのです。
セザンヌの風景画をご覧になってください。いたるところにそんな仕掛けが仕組まれていますよ。セザンヌの風景画は、 東洋の山水画とまったく同じ性格を持っています。いつまでもいつまでも絵の中を歩きつづけることが可能です。
 水浴図もすばらしいですね。これは女のヌードを楽しむための絵ではないのです。
セザンヌの心を楽しむ絵画なのです。ヌードモデルはセザンヌの目の前にはいないのです。リアルなヌードが描けるはずはありません。
彼にあるのは、遠い遠い記憶と、数十年前、画学生のころアカデミースイスで描いた、古びたヌードクロッキーだけでした。彼は水浴図を
生涯の傑作にするつもりだったので、何枚も何枚も下絵を描きましたが、さすがに困難に陥って、親しい友人にこう訴えて、友人を絶句さ
せています。「ねえ、君は女性を見ていらっしゃるのだから、せめて写真でも持って来てください。」
水浴図もすばらしいですね。これは女のヌードを楽しむための絵ではないのです。
セザンヌの心を楽しむ絵画なのです。ヌードモデルはセザンヌの目の前にはいないのです。リアルなヌードが描けるはずはありません。
彼にあるのは、遠い遠い記憶と、数十年前、画学生のころアカデミースイスで描いた、古びたヌードクロッキーだけでした。彼は水浴図を
生涯の傑作にするつもりだったので、何枚も何枚も下絵を描きましたが、さすがに困難に陥って、親しい友人にこう訴えて、友人を絶句さ
せています。「ねえ、君は女性を見ていらっしゃるのだから、せめて写真でも持って来てください。」
水浴図の中でセザンヌは、アイボリー、オレンジ、水色、緑色を巧みに用いて、寒暖対比だけで裸婦のボリュームは表現 しています。じっくり見ていると、陶器色の肌の女性たちがなまめかしく感じられてきませんか。私にはセザンヌのすがすがしいエロスが、 微笑ましく思われます。水浴図を見ながら、裸婦たちの手の方向を、脚の方向を、頭なら頭だけを、木の枝なら木の枝だけを、目で 追ってみてください。絵の中で、目はくるくるといろいろな大きさの輪を描きながら、セザンヌ爺さんの桃源郷をさまようのです。水浴図、 それはセザンヌ理論の壮大な、最後の実験場といえるものです。
静物画も同じです。ただ私は、今回初めて、セザンヌの静物画に息苦しさを覚えました。私の一番好きなセザンヌは、 長いことずっと静物画だったのですけれど。もちろん、静物画も他の絵と同じように、視線を誘導してくれるのですが、二回り、三回り ぐらいで終わってしまう気がするのです。空間の奥行きが浅く限定されていることと、静物画だけが、徹頭徹尾、人為的に配置された空間 だからでしょうね。完成度の高さが、息苦しさを助長しているかもしれません。
肖像画の空間も深くはありませんが、いくらセザンヌが性格描写に無頓着でも、やはり人間を描く以上一個の人格は 現われてきますから、その人間存在の深さの方にも目が行くために、息苦しさを感じなかったのだと思います。またもちろん、対象に、 この色があるから色を置くというのではなく、画面のこの部分にこの色が欲しいから色を置く、といった態度を貫いているのはいうまでも ありません。
セザンヌは、対象を見ながら、一本の線を引きます。そして、また対象を見ながら次の線を引くときに、最初の一本と 正しく響き合うように徹底的に吟味するのです。一つの色を置くと、その隣りに置くべき色をじっくりと検討する。この繰り返しです。 向こうの色をただ、こっちに持ってくるのではなく、画面と納得いくまでやりとりしているのです。セザンヌの遅筆の理由はまさにこれで した。一筆の決定に15分かける、そんなことはざらだったといいます。画商のヴォラールがモデルを務めたときには、115回通い つめても完成しませんでした。気の毒なことに、セザンヌはリンゴのように不動であることをヴォラールに厳しく要求しましたが、モデル が疲れるといったことには全く気がまわらなかったそうです。
* * *
さてこれまで述べてきたことは、古今東西あらゆる画家が多かれ少なかれ用いてきた手法です。しかし、セザンヌは明確 な意図を持って、これらの手法を徹底的に使いこなした人だということができそうです。では、真にセザンヌの独創と言えるものは何で しょうか。
セザンヌの独創とは、自分でもたびたび述べているとおり、文学性といわれるものを一切排除して、造形性だけで絵画を 成立させたところにあります。つまり対象の魅力に頼らないということです。
私は、画家の制作態度としては、セザンヌが描く対象を選び抜いたようには思えないのです。例えば、風景を描くときに 彼は、まず普通はこんな場所は選ばないだろうという場所にも平気で画架を据えています。描かれた場所の写真を見ると、私などでは 見過ごしてしまいそうな場所ばかりです。誰も描かないような場所を選んだセザンヌの目が独創的だったというのではありません。そう ではなくて、彼にとっては、出会ったものが自分の造形実験にふさわしいものであればそれでよかったということなのです。彼は、今まで の画家たちのようなやり方では、対象を決して吟味してはいません。
人物画でもそうです。彼は獲得するのに骨が折れるようなモデルは使っていません。親兄弟、妻子、使用人、友人や礼賛 者、そして自分といったところです。先に述べたとおり、水浴図のヌードも、30年か40年前のヌード・クロッキーをもとに構成して います。そして、彼の人物画は人生を暗示するものではなく、裸婦はエロスを目的とするものでもない。風景画や静物画は、リアリティの 再現を目的としてはいないのです。
セザンヌが、「リンゴ一個でパリ中を驚かしてやりたい」 と言ったのも、対象の魅力に頼らず、彼の世界観と、造形性だけで新しい絵画を創造するという意味だったのです。この立場は新しい。 全く新しいものでした。印象派の旗手モネの作画態度はセザンヌに近いところがありますが、彼の絵の中に対象への憧れは存在します。 対象の魅力は先にあります。
しかし、セザンヌにはセザンヌの造形世界が先にあって、そのあとに対象がくっついて来る。対象に魅せられてはおらず 、それはただ存在しているだけです。彼は、「 モチーフをさがしに行く 」 といいます。こういうものが描きたいのでさがしに行くのではないのです。自分の造形世界を表現するためのきっかけとなるモチーフ (導調)をさがしに行くというのです。
こうしたセザンヌの態度は、絵画の自律(自立)をうながしました。対象の呪縛からの自律です。彼が、対象への憧れと いうようなウェットな部分を絶ち切ったことで、クールな20世紀芸術が生まれたのです。堰を切ったように新しい絵画の奔流が流れ 始めたのです。セザンヌが近代絵画の父と呼ばれる所以もここにあります。彼の絵画がフォービズムを生み、キュービズムを生み、 アブストラクト、ダダ、シュールレアリズム、未来派、表現主義、絶対主義、抽象表現主義、ポップアート、ミニマリズム、コンセ プチュアルアートへとつながっていくのです。ブラックもピカソもヴラマンクも、キルヒナーもモンドリアンも、ゴーキーでさえも一時期、 セザンヌ様式の絵を描いています。
これらすべてに共通していえることは、対象への憧れが弱まっていることです。彼ら独自の表現があらゆる対象に先行 しているのです。(エコール・ド・パリの画家たちに対象への憧れは強いですが、モディリアーニやスーチンも、ジャコメッティも、 セザンヌ風を描いています。)
彼ら一人一人は新しい。でもだんだんと時代が進むにつれ、魂をゆさぶるようなものは少なくなって来ました。80年代、 90年代のアートを見ると、もはや映像を使おうが、音を使おうが、心を豊かにする芸術ではなくなって来ました。あまりに特異な表現 にこだわって、先を急ぐあまり、どうも地に足のついた芸術ではなくなって来たように思います。私自身は、もう一度セザンヌの立脚点に たち帰るか、若しくはセザンヌ以前に戻らなければいけないような気がしています。
(99/12/21)