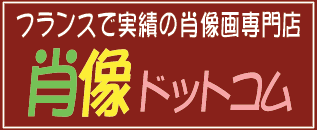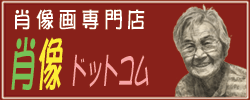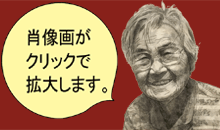【一枚の絵の歴史を語らう】

水墨画「古岩屋図」
この絵は愛媛県浮穴郡久万高原町に位置する景勝地「古岩屋」を描いたものである。かつては、いや今もさうであるかもしれぬが、四国霊場八十八ヶ所の第四十五番札所、海岸山岩屋寺の寺域であつた。
今から32年前、昭和から平成の世に代はつて二年目の1991年、32才の私を未踏の地、四国は伊予の古岩屋へと導いたのは、国宝「一遍聖絵(いつぺんひじりゑ)」と呼ばれる絵巻物である。浄土三宗の一つである時宗の開祖、一遍上人(1239-89)の生涯を描いてゐる。
これは一遍没後の十年忌に、最初の弟子で甥だつたとも云はれる聖戒によつて完成された、日本美術史上中世を代表する傑作とされている。
聖絵には上人が遍歴した全国各地の名勝・社寺の景観が、美しい自然とあらゆる階層の民衆の姿と共に克明に描かれる。
伏見帝の世の権力者、関白従一位・九条忠教(ただのり)の勧めに拠つて、聖戒が企画。大和絵の名手・土佐法眼円伊が絵を描き、書の名門・世尊寺家の始祖・藤原行成から10代目の経尹(つねただ)が各巻の外題の筆を執つた。詞書(ことばがき)も当代一流の四人の手に成るものと云われている。
その聖絵の冒頭に近い第二巻に収められている山水画を見たとき、私の目は釘付けになつた。
そこに描かれていたのは、高さ数十メートルはあらうか、垂直に屹立する三峰の奇岩であつた。頂上には赤い鎮守の祠(ほこら)が設置され、最も高い奇岩には長い梯子が掛けられていた。
二十一段の梯子の上段には若い聖戒が、それに遅れて下段には一遍が頂上を目指している。画面の調子は、明るい黄土や褐色地に青や緑が彩られ、ところどころにしろや赤や橙が点ぜられて、何とも美しい。
このように描かれた日本の景観を初めて見た私は、この地を訪れ、絵に描いてみたいと願はずにはをれなかつた。
ちなみに第二巻のこの段は、「菅生の岩屋」の情景とされ、一遍上人開眼の地と記されてゐる。
一遍上人は元々、源平合戦でその名をとどろかせた河野水軍の総帥・河野通信の孫、河野通尚(幼名松壽丸)として伊予国浮穴に生を受けてゐるので、菅生の岩屋は生来の在所に程近い。
加へてこの地は、敬愛する讃岐出身の弘法大師空海ゆかりの地でもあつた。